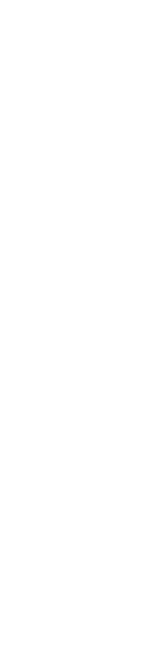New Articles新着記事
-

- 審美治療で人気オフィスホワイトニングはどんな人におすすめ?
- お金がかかっても効果重視の方 ホームホワイトニング・セルフホワイトニングなどと比べて、オフィスホワイトニングはお金がかかってしまいます。 しかし、歯医者で施術を受けられるので良質な薬剤を使えますし...
-

- 矯正をするならマウスピース矯正がおすすめ!知っておきたい基礎知識
- マウスピース矯正とはどんな治療法? 矯正と聞くと、ワイヤーや金具を使った矯正器具が思い浮かぶ方もいるでしょう。 こうした装置から、矯正には痛そうなイメージがありますよね。 しかし、マウスピース矯...
-

- 安いと評判の矯正歯科は大丈夫?コスパの良いクリニックの比較ポイント
- 自分が行いたい矯正治療の経験が豊富であるか 矯正歯科を選ぶときは、安さよりも、自分が望む治療の経験が豊富であるかどうかを重視しましょう。 そのほうが、納得のいく治療を受けることができます。 治療...